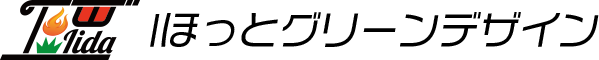今日は、骨材の搬入と石の乱貼りを貼りました。

アプローチとなる、乱貼りです、色を2色使い濃淡を付けて行きます。

乱貼りは、石のジグソーパズルみたいで、施工してると大体、どこのお施主様も見に来て、感心したり、どうやるのか、聞いてきます。
この乱貼りには、やってはいけない禁止事項があります、4つ目地と言って十字に目地がならないように、貼って行きます、また芋目地と言って、芋のツルみたいに、長く通しては、いけません。
もちろん、わざと禁止事項を、施工して、タイルみたいに貼って行く方法も見たことがあります。
だが、基本は自然の石を想像して、石を重ねるところに、気を使っていき、よりきれいに見えるように、大きいしと、繋ぎの石と、三角、四角、丸、長細い、などをバランス良く貼って行きます。

バランスと言っても、バラバラと言う意味ではなく、歩く歩幅に大きな石を置き、周りを繋ぎの石にしたり、景観を切り取り、7:5:3の法則で、大きな石と小さな石とその真ん中の石を貼って行くと、より景観がしまってきます。

僕の貼り方は、主石となる石を置き、それに合わせて、7:5:3を頭でイメージしながら、貼って行きます。
多分、どの職人さんも、やり方があって、法則を作っていると思いますが、たかが石貼りですが、とても奥の深い、お庭づくりの礎のようなものです。
このように、こだわりを持って、作業して行かないと、音のするお庭は作れません、良いお庭には、必ず音が聞こえそうな、意志と言うか、作った人の顔が見えそうな気になります。
日々のすべての事が、お庭作りのヒントになって、出会う人すべてが、今の必要なプロセスとなって行くのでしょう。

全ての仕事は人を育てて、その人の為に、置かれた通る道です、その道のプロを目指しているのなら、新しい自分の道を見つけて行かないと、いけませんね。
いつもブログを読んで頂きありがとうございます。